第7回 未来予測の歴史②
第2次未来予測ブーム(1960~80年代)
20世紀初頭の未来に対する関心は、1929年の世界大恐慌、その後の第2次世界大戦の影響により一旦冷え込みますが、終戦後にブームは再燃します。第1次未来予測ブームは、ほぼ空想レベルでの関心でしたが、未来予測をより実用的に活用したいというニーズが次第に高まります。
第2次世界大戦後の東西冷戦に伴う軍事緊張が高まる中で、予測技術は徐々に発展し、その後民間レベルでの応用、活用にまで拡がって行きました。1960年頃からは、経営戦略や企業経営にまで未来予測を取り入れようというニーズも生まれました。未来予測を技法化、メソッド化しようとする動きです。
その最初の動きが世界初のシンクタンクとして著名なランド・コーポレーションによるものです。ランド社の創設は1945年。当初の目的は、米国空軍のための軍事技術情報予測のためでしたが、その後領域を広げ、いくつかの未来を構想するための技法を開発しました。シナリオ・ライティング、コンピューター・シミュレーション、技術的未来予測、デルファイ法、プログラム予算、費用対効果、システム・アナリシスといった手法は同社が開発したものです。デルファイ法は、1964年に同社が発表した『長期予測の報告書』において、2000年までに実現可能な技術は何かを予想するために同社が開発した技法です。
これ以外にも、「システム・ダイナミクス」、「VALS類型論」など、未来を予測するためのさまざまな技法の開発がこの時代進みました。
1965年にはダニエル・ベルを議長とする「米国アート&サイエンス・アカデミーの200年コミッティー」が組織化され、全米の大学研究者、政府関係者、大企業経営者が集結し未来レポート『ダイダロス(迷宮):2000年に向けて、ワーク・イン・プログレス』が発行されました。同じく65年には「世界未来学会」が組織化され、翌年にはオスロ(ノルウェー)で「世界未来研究組織」の第1回会議が開催されました。日本でも、「日本未来学会」がこの時期生まれました。
未来学者と称する多くの人々がマスコミやメディアに登場し、未来予測に関する書物を発表し、ベストセラーとなったのも同じくこの時期です。代表的なものとしては、ダニエル・ベル『脱工業化社会の到来』(1975)、ハーマン・カーン『大転換期』(1979)、アルビン・トフラー『未来の衝撃』(1970)『第三の波』(1980)、ジョン・ネイスビッツ『メガトレンド』(1982)などがあげられます。
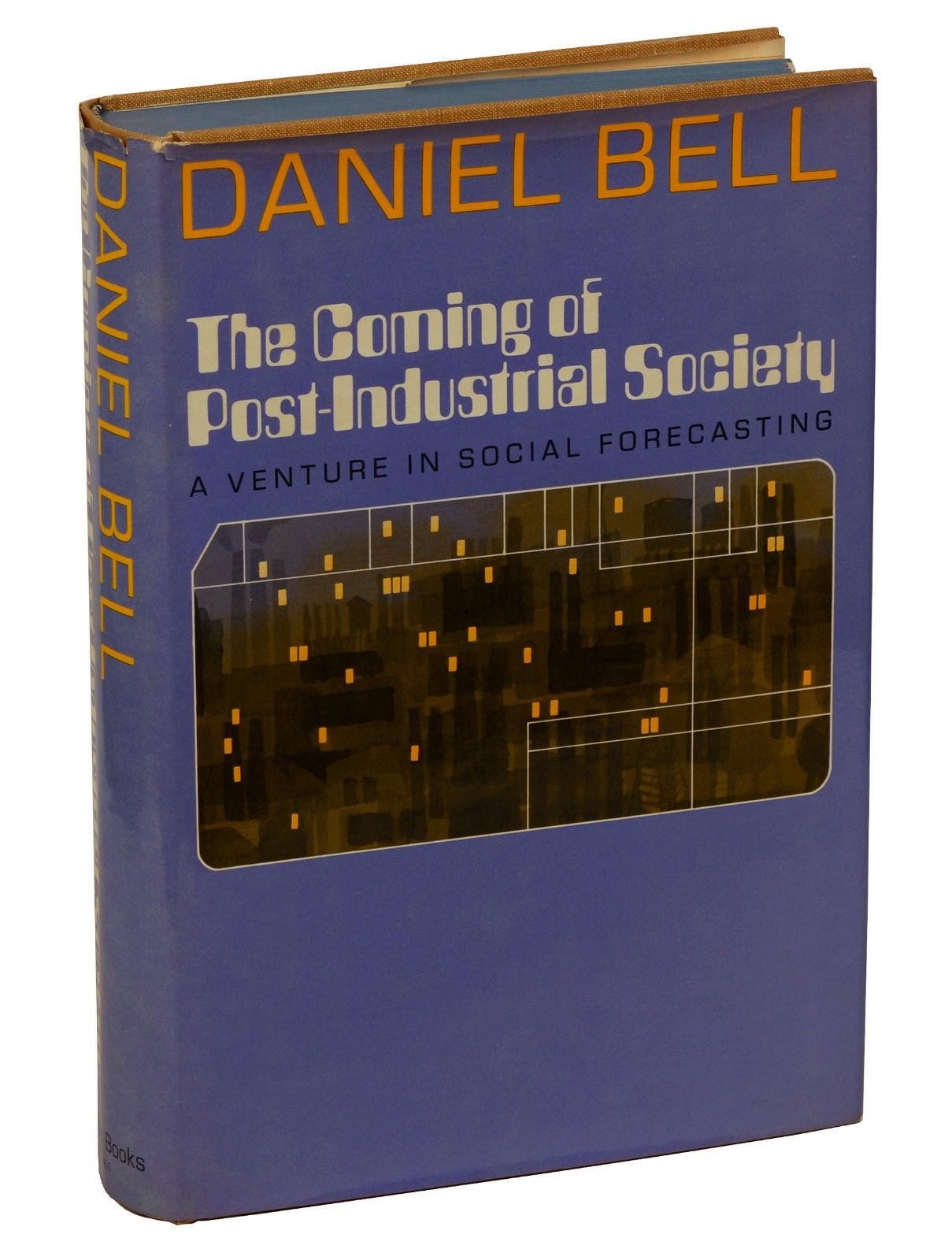
ダニエル・ベルは社会学者、ハーマン・カーンは軍事理論と一般システム理論の専門家、トフラーとネイスビッツは作家と、出自は異なりますが、いずれも膨大な知識データを元に今後の社会がどのようになるかを大胆に予測しました。いわゆる知の巨人的な未来学者が活躍した時代だったと言っていいでしょう。日本では、SF作家の小松左京や元官僚の堺屋太一が同じくこの時期に注目を浴びました。
この時期の代表的な未来予測本をいくつか紹介しましょう。
アルビン・トフラー『第三の波』は、当時から見た未来状況をある程度正しく予想できたもののひとつです。本書では社会を根底から覆す大変動を「波」と表現し、人類数千年にわたる農業の時代を「第1の波」、産業革命以降の工業社会時代を「第2の波」としたうえで、現在訪れつつあるのは「第3の波」であると語ります。第2の波「工業社会時代」の特徴は、規格化、分業化、同時化、集中化、極大化、中央集権化などのキーワードに象徴されるもので、産業中心主義を中心基盤としながら、そこに家族や経済、政治などの各種システムなどが動くものでした。
第3の波は、こうした、いままでの家族や経済、政治システムをゆるがし、価値体系を粉砕するものであると彼は語ります。予兆を再生可能エネルギーの伸張、量子電子工学や情報理論、分子生物学宇宙工学などの新学問分野やコンピュータとエレクトロニクスの可能性などに見てとります。それ以外にも第3の波の兆候として、マスメディアの終焉、多品種少量生産の進展、規格化からの脱却、住宅のエレクトロニック化、家族形態の多様性、在宅勤務の増加、企業の社会的責任の増大などを指摘しています。
これらの動きが第1、第2ほどの大きな波であったかどうかはともかく、これらの指摘事項は現在に繋がる工業社会時代の価値感の大きなゆらぎの兆しであったことは間違いないでしょう。
ちなみにこうした主張の中で、発表当時に最も話題となったのは、「プロシューマー(生産=消費者)」というキーワードでした。DIY市場の伸張などで「消費者は単に消費するだけではなく、生産の過程にまで入り込んできている」として「消費者主導型」商品が主流となる、との指摘は、マス・プロダクションがまだ全盛期であった当時、この発想は全く新鮮なものでした。現在は、多くの人々がPCやアプリケーションを操り、3Dプリンターを使ったものづくりにチャレンジしたり、アニメや音楽製作を楽しんでいます。まさにプロシューマー全盛時代と言えるかもしれません。
自らをソーシャル・フォアキャスター(社会予報士)と称したジョン・ネイスビッツが、10の未来潮流を予測したのが『メガトレンド』です。ネイスビッツは、米国で連邦政府やIBMなどの顧問、リサーチ機関の顧問などを務めていました。本書においてネイスビッツは、情報化社会の進展、経済のグローバル化、ネットワーク型社会の到来、多様性の時代の到来などを予測しました。それらの中で、最も注目を浴びたのは、「ハイ・テック/ハイ・タッチ」というキーワードでした。時代が技術寄りに(ハイ・テック)なればなるほど、その反動として人間的で自然的な感覚のもの(ハイ・タッチ)が必要とされるという予言は極めて示唆に富んだものでした。当時、ネイスビッツはメガトレンドを導き出すための、重要事項やトレンドを指摘しトレースし炙り出していくために、毎月6千にも上るローカル・ニュースペーパーをモニタリングしていたそうです。現在ではこうした作業は検索機能を使えばより簡単にできるはずです。
本書での事例、「ワード・プロセッシングの高度な技術がオフィスに導入されるにつれて、手書きのノートや手紙が復活してきた。」は、近年のモレスキン(MOLESKIN)ノートなどの手書きノートの人気を見ても確かにと思わせるものです。また、一方でiPadなどのタブレット型ノートブックのペンシル利用はそうしたハイタッチ志向をハイテックが再度取り入れようとする動きにも見えます。
当時のフォアキャスターたちの書いた書籍を改めて読み返してみると、確かに当たっていると思わせる項目もありますが、一方で大外れの予測もあります。例えば、ハーマン・カーン『超大国日本の挑戦』(1970)、エズラ・ヴォーゲル『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(1979)は、当時急激な経済成長を成し遂げた日本成功の秘密を分析し、「21世紀は日本の世紀」(カーン)と予測しましたが、その後の結果は既に皆さんもご承知の通りです。
いわゆる当時のトレンド(傾向)だけをそのまま直線的に伸ばした未来予測が必ずしも正しい結果をも導くわけではないという事をこの事実は示していると言えるでしょう。
この時代の未来予測の特徴のひとつに「パラダイムシフト」というキーワードを挙げることが出来ます。パラダイムとは、科学史家・科学哲学者のトーマス・クーンが提唱した科学史及び科学哲学上の概念で、”時代を支える大きな枠組み”がパラダイムであり、これが大きく変化することがパラダイム・シフトです。「第3の波」「メガ・トレンド」などは情報化の進展により時代が劇的に変わると予測しましたが、こうした予測態度はマルクスの唯物史観に影響されているのではないかという指摘もあります。一方で、こうしたキーワードで時代の変化を表現することは、変化特徴が端的にわかりやすく理解できるというポイントも指摘できるでしょう。
これらから、われわれが得られることが出来る示唆は、われわれが予測でき得る未来の姿は、「そのときまでに我々が知り得ている事実に大きく制限される」という事実でしょう。言い換えれば、「社会構造を大きく変えてしまうほどの大きなイノベーション」、すなわち不連続な変化は予測するのがなかなか難しいということです。
実際、先に紹介した各種未来予測の書籍の中で、インターネットの登場とこれがもたらした革新的な社会変革が予想できた人は皆無でした。インターネット普及の契機となったWorld Wide Webシステムの発明は1990年。スマートフォンを発明したアップル・コンピュータも創業はしていましたが、まだスタートアップ間もないガレージ・カンパニーに毛が生えたほどの存在でした。
時代への警鐘としての未来予測
この時代には、技術発展による未来予測だけでなく、経済成長の限界に警鐘を鳴らす動きもいくつか出てきました。その代表事例が、レイチェル・カーソン『沈黙の春』(1962)やローマクラブ『成長の限界』(1972)です。
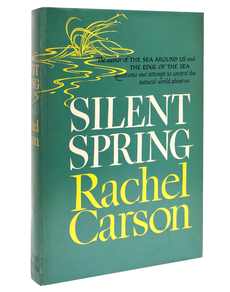
『沈黙の春』は、米国の生物学者であったカーソンが、DDTなど農薬で使用されている化学物質の危険性を訴えたもので、当時の大統領ケネディが強く関心を示し、これがきっかけとなり、現在に続く環境保護運動の高まりやアースデイ活動、引いては現在のSDGsなどの動きに繋がっていきました。
ローマクラブ『成長の限界』は、オリベッティ社の副社長アウレリオ・ベッチェイ博士の主導のもと、マサチューセッツ工科大学のデニス・メドウズを主査とする国際チームに研究を委託し、システムダイナミクスの手法を活用してまとめられたもので、人口増加や環境汚染などの現在の傾向が続けば、100年以内に地球上の成長が限界に達すると警鐘を鳴らしたものです。こうした、地球環境の将来像に警鐘をならすといった活動もこの時期に生まれてきたものでした。
第3次未来ブーム(2010~)
さて1970年代から80年代初頭にかけて盛り上がった未来予測ブームでしたが、その後、未来に対する一般人の関心は、一旦萎んでしまいます。それにはいくつかの理由を挙げることができます。
ひとつは、当時人々が思い描いていた明るく豊かな未来像が、夢物語であったと気づき始めたことです。第2次未来予測ブームが起こった時期は、オイルショックもあったものの世界の先進諸国が高度経済成長を果たした時期とほぼ重なります。1980年代となると経済成長は一段落し、消費の多様化・成熟化が進む一方で、未来に対する期待感が次第に失われて行きます。
明るい未来像ではなく、退廃的で絶望的な未来像、いわゆるデッド・テック・フューチャーが現れてくるのがこの時代です。それを代表するのが、リドリー・スコット監督による『ブレードランナー』(1982)、大友克洋の「AKIRA」(1982-1990)などで、これらに象徴されるような終末的な未来像が幅をきかせるようになります。ジョージ・オウエルが1994年に執筆した未来監視社会小説『1984』が描いた時代にそうしたディストピア感が蔓延したのは、何らかの偶然とは言え、奇妙な符合を感じさせるものでした。
その後のパソコン、インターネット・ブームなどを経て、未来に対するポジティブな新しい未来像が再び提示されてくるようになったのは、ミレニアムも過ぎた21世紀以降のことです。
2010年頃からはじまり現在に至る人工知能、ロボット、自動運転、ビッグデータなどの新しい技術革新とともに再び未来予測ブームに火が付きました。
第3次未来予測ブームの特徴として挙げられることができるのは、第1次、第2次のように偉大な個人の未来学者の考察による未来予測が行われる一方で、さまざまな収集データに基づきつつ未来を予測するという集合知を集める(ホライズン・スキャニング)的な手法がもう一方の動きとして広がっていることです。これは、まさにインターネット時代的な予測手法の特徴でもあると言えます。当然、将来的にはさまざまな未来予測を人工知能やAIが行うということも十分考えられますが、現在は、天気予報などの一部の特定分野での活用が中心ですが、いずれAIが未来予測を行う時代がやってくるかもしれません。
こうした動きと連動するかのように、「未来はこう変わる」と断言口調の、ある意味で“単純な”未来予測ではなく、多面的に未来を理解し、逆に未来をポジティブに変えていこうとする未来予測の動きがこの時期に同時に起こり始めました。いわゆる「未来予測(Foresight)」から、「未来研究(Future Study)」への変化です。
この時期の未来研究に多大な貢献を果たしたのが、オーストラリアのフューチャー・スタディーズ・センターの創設者リチャード・スロウファー(Richard A.Slaughter)です。彼は未来予測の役割は、「まだ時間的余地があるうちに、持続可能な社会への移行を完了させるために知覚させるための仕事である」と捉えました。彼の書籍『The Foresight Principle』では、未来予測とは「未来を予言する能力」ではなく、「望ましい変化を促すための貢献である」と主張しています。
フューチャー・インパクト(デンマーク)のフューチャリスト、コーネリア・ダイヘイム(Cormelia Daiheim)は、2005年以降の実践的な未来研究の特徴として、①質的アプローチと量的アプローチの統合、②ITベースによる自動化アプローチ、③オープンでクラウドソースされたアプローチ、④経験的な先見性という4つの特徴を挙げています。これらの多くは、インターネット、ビッグデータ、AIといったテクノロジ−環境へのアクセスが容易になったことから生まれてきた新たな手法です。
こうした動きに加えて、近年のフーチャー・スタディーズの特徴として挙げられるのは、かつてのような単線的な(ひとつの)未来を描き出すのではなく、望ましい未来のあり方を考えていくための方法論が中心ということです。
加えて、「個人の(偉大な)フューチャリストが未来を考えるスタイル」ではなく、数多くの人々の知恵を結集して、「多数で未来を考えようとするスタイル(集合知による未来構想)」となって来たところも近年の未来研究の特徴のです。このような先進的な未来研究の成果の一部も今後紹介していきたいと思います。




